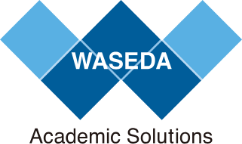少子化や進学率の頭打ちにより、
日本の大学は大きな岐路に立っています。
そのような状況を
ITの力で全方位から支援する
早稲田大学アカデミックソリューション
(以下、WAS)
のIT推進部には、
IT未経験から目覚ましい成長を遂げ、
ITスペシャリストとして活躍する
多くのメンバーが在籍しています。
卒論をスマートフォンで書くなど
パソコンもほぼ触ってこなかった学生が、
どのようにITスペシャリストへと
進化を遂げたのかー。
システム開発統括チームの
M.N.さんにお話を伺いました。

2021年入社
IT推進部 IT-Xチーム
M.N.
*所属チームはインタビュー当日の配属先です

IT未経験からの挑戦
大学教職員の業務を
劇的に変えるシステムの開発へ

IT企業を中心に就職活動を行い、2021年にWASに入社されたと伺いました。IT業界に興味を持ったきっかけがあれば教えてください。
ITに興味を持ったきっかけは、様々な企業のインターンに参加するなかで、日々当たり前のように使っているデジタル技術やITも人の技術と努力の上に成り立っていると気づいたからです。
そうした当たり前に使われているシステムをつくる知識を身につけて、人々の生活をもっと便利にしたいと思い、IT業界を中心に就職活動を行い、最終的にWASに入社することを決めました。
入社後は興味のあったIT推進部への配属となりましたが、学生時代は卒論をスマートフォンで書くなどITとは無縁だったと伺っています。IT未経験でIT推進部に配属されることに不安はなかったですか。
もちろん不安はありました。しかし、システム開発やソフトウェア、ITコンサルなど複数のIT関連企業でのインターン中に、IT未経験でも活躍されている先輩方に出会い、スキルは後から身につけることができると聞いていたので、なんとかなるだろうと信じていました。
実際、配属後にどんどんとITスキルを身につけ、入社4年目とは思えないほどの活躍をされているそうですね。入社後はどのような業務を担当されてきましたか。
1年間はRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)に関する知識と技術の習得に時間を割きました。2年目以降は大学の教職員が使用する、経費の精算や請求書・領収書の管理といった経理処理業務のデジタル化を実現する「経理アプリ」のプロジェクトに加わりました。このプロジェクト発足の背景には、改正電子帳簿保存法への対応もありました。
私はシステムエンジニアとして、システムを設計する段階から完成までの一連の流れを経験しました。完成後は本システムの主担当として、不具合が起きた際の対応や機能改修などを行なっています。
経理アプリは大学の教職員3,000人ほどが使用する重要なシステムだと伺っています。このシステムについて詳しく教えてください。
経理アプリには、業務のデジタル化に加え、大学の教職員が抜け漏れなく対応しなければならない、経費の精算や請求書管理といった日々の経理業務の手間を効率化する狙いもあります。
システム化される前は、研究のために教員が何かの道具を買うと、紙の請求書を学部の事務所に持ち込み、経理担当者に処理を依頼していました。請求書を受け取った担当者は経理処理用のエクセルに必要事項を入力し、承認のための用紙を印刷。学内便を使って、その用紙に複数人の承認印を得て処理が完了するという非常に長い工程があったのですが、それらすべての工程をデジタル化したのが経理アプリです。
デジタル化すべき工程も多く、様々な役割の人が関わる複雑なシステムですね。システムが完成するまでにやるべきことはたくさんありそうですが、開発において具体的にどのような業務を担いましたか。
この経理アプリの立ち上げからプロジェクトに関わり、会議に参加していました。まず、上司と大学の経理担当や情報システム担当の職員でこのシステムにどんな機能が必要か、記入から承認までの流れをどのように進めるかといった要件を定義しました。そこで決まった機能、工程を設計書に落とし込むことが私の最初の仕事でした。
続いて、社内に常駐するプログラマーに決めた設計書の内容をプログラムで組んでもらい、スケジュール通りに開発が進んでいるかの進捗管理を行いました。同時に、書いてもらったプログラムが設計書通りに正しく稼働するかを確認するためのテスト仕様書を作り、実際に一つ一つの機能や工程の動作テストの検証も担当しました。
1日も早く自分で
解決策を提示できるよう
小さな「わからない」も残さない

入社2年目から開発会議に参加し、要件を設計書にまとめるなど重要な役割を担ってこられましたが、プロジェクトへ参加直後から活躍できたのでしょうか。
プロジェクトに参加した直後は、専門用語ばかりが出てくる会議で話されている内容も理解できないことが多かったです。開発背景も把握できていないことが多く、なぜこの機能が必要なのか、なぜこの工程が必要なのかなど、わからないことばかりでした。
そのような状態から抜け出すために、どんなことに取り組みましたか。
「なぜこうなのか」という疑問が出てきたら、わからないことを1つずつ潰していくしかありません。わからないことが発生したら、まずはインターネットで調べるのですが、そこに書かれてある専門用語もわからないことが多くありました。専門用語をさらに調べ、それでもわからないときは、同じチームの先輩に教えてもらうことを繰り返しました。
業務時間内だけで足りない場合は、業務時間外にも解説YouTubeを見るなど、自分なりに学習もしました。
しかし、知識が足りない分、今目の前にある課題をどうしたら解決できるのか、ITでできる解決策を提案することができません。「持ち帰って検討します」としか言えないことが悔しかったので、1日も早く「その課題にはこんな解決策があります」と自分で答えられるようになりたいと思っていました。
今回の経理アプリでも、特に教員の事務作業にかかる時間を削減することにこだわって開発されたとのことですが、具体的にどのような点にこだわったのか教えてください。
教員は研究と教育が本業です。システム要件を考える際には、本業以外の事務作業の手間をどれだけ減らせるかを考えなければなりません。自動選択にして教員が入力する項目を減らしたり、忙しい教員がマニュアルを見なくてもすぐに使いこなせるよう、わかりやすい画面説明を加えたり、徹底的に教員ファーストで考えました。
こだわりが詰まった経理アプリを使われた教職員の方からの反応はどうでしたか。
概ね好評です。特に教員が入力する項目を減らしたことや、マニュアルを読まなくても使いこなしてもらえるように画面説明を丁寧に書いたことなど、こだわった部分が使いやすいとの声をもらっています。
早稲田大学には様々なシステムがありますが、他の一部のシステム画面も経理アプリに合わせてほしいとの要望をもらうくらい高く評価されているようです。
さらなる高みを目指して
積極的な提案
論文執筆へ

経理アプリの開発を通して、様々な業務を経験されたと思います。その中で最も成長を感じた瞬間はどんなときですか。
自分のなかでターニングポイントになったのは、経理アプリの結合テストの仕様書を作成し、全体のテスト検証を統括していたときです。システムを一通り作り終えると、全ての工程を実際に動かす「結合テスト」を行います。結合テストとは、何十個もの機能の動作確認を1個ずつ確かめるだけではなく、システム全体の機能が仕様通りに動き、正しい工程を進むのかの検証です。
結合テストを統括する立場としては、システム全体の各機能の仕様をすべて理解していなければなりませんし、このシステムを使用する方がどのような動きをするのかを把握してテストシナリオを組み、各検証結果が正しいのかを確認しなければなりません。
今まで「これは何のためにやってるんだろう」「これをやらないとどうなるんだろう」といった断片的に集めていた知識が、この結合テストを通してピタッと結びつき、全体像を理解できた瞬間だったように思います。
システム開発を一通り経験して、ご自身の成長も実感できたとのことですが、システムは完成して終わりではありません。作ったシステムを有効活用してもらうために、完成後はどのような取り組みを行ないましたか。
システムを導入して1年ほど経った頃、溜まったデータを集めて振り返りを行いました。これまで自分でデータ分析を行なったことはなかったのですが、データ分析ツールを使い、1年間で処理が行われたデータの件数やシステム導入の目的としていた請求書の電子化率、取引先毎の紙請求比率などを明らかにして、大学に報告と提案を行いました。
具体的にどのような提案と報告を行なったのですか。内容を教えてください。
取引先別の電子請求書の比率についてです。データを分析すると、早稲田大学が取引している主要取引先の上位5社がほぼ紙の請求書であることがわかりました。その5社すべての請求書を電子化することができれば、それだけで全処理の3割を電子化することができます。
この影響は大きいと考え、大学職員にその5社に電子化を依頼するように提案しました。交渉の結果、2社は電子化に移行できそうとの話があるので、提案してよかったと思っています。
この経理アプリ開発による業務削減効果や、システムに溜まったデータ活用の取り組みが社長の目にも止まり、これらの成果を論文にまとめる話が出ていると聞きました。今後の発表予定が決まっていたら教えてください。
はい、この成果に関する内容は2024年12月に奈良県で開催される大学業界のIT学会で発表する予定です。最近はその学会発表に向け、システムに溜まったデータを活用して、職員の残業時間や休日出勤を削減したことや、機能の性能評価による数百万円規模のライセンス費用を削減したこと、さらなる機能開発に活かしたことなどをまとめていました。論文執筆は初めての経験なので、とても難しかったのですが、先日やっと提出することができました。
周囲のサポートが成長の源
アグレッシブな挑戦で
未来を拓く

入社後、早い段階から大きなシステム開発に携わり、完成後も積極的にデータ分析や大学への提案を行うなど、経理アプリのリードをされていますが、IT未経験から4年でここまで成長できたのはなぜだと思いますか。
周囲の存在が大きいです。ITに関する専門用語さえもわからない状態でシステム開発会議に参加していた私に、先輩方はわからないことはいつでも、なんでも聞いてほしいと親身になって寄り添ってくれました。このサポートのおかげで、たくさんの人から聞いた情報を自分の知識として蓄えることができたと思っています。
しかも、ガチガチにマネジメントするのではなく、自分で考えることを尊重してくれます。業務時間中にITに関する調査や勉強ができるなど、当時の業務には直接関係のない、インフラやサーバー、ネットワークといった分野の勉強などもできたことで、知識が深まっているように感じます。
4年目で論文執筆まで遂げた今、今後はどんなことに挑戦したいですか。
これまでは設計書の作成やシステムテストなどを主に担当してきましたが、今後は自分でプログラムを書くことにも挑戦したいです。どんなシステムにするのかを考えて、プログラムを書いて、システムテストで検証するといった一通りの流れを全部自分でできるようになることを目指しています。
システム開発に関する一連の工程に携われる、システム開発統括チームの仕事の面白さはどこにあると思いますか。
この仕事の面白さは、自分たちが作ったシステムが意図した通りに動くことで、利用者の業務のどこかが効率化されたり、ラクになったり役に立ったと実感できることです。
直接利用者と接する機会も多いので、障害やエラーのご指摘や、もっとこうしてほしいという要望をもらうこともありますが、「システムのおかげで仕事が早くなりました」「あなたがいなかったらできなかったです」と言われる瞬間が一番の喜びです。
ご自身もIT未経験からシステム開発へ挑戦され、目覚ましい成長を遂げられています。最後にIT業界に興味を持つ方にメッセージをお願いします。
私もまだ入社して4年目で勉強中の立場ですし、新人を除くとチームで一番下なので、先輩たちに教えてもらうことの多い日々です。しかし、質問されることも増えてきたので、少しずつですが頼りにされていると実感しています。
これは、周囲のサポートや自由に勉強できる環境だったことはもちろん、早くからプロジェクトに参加して、自分が手を動かす経験を積めたからだと思っています。
学生時代にITの開発プロジェクトを回したことのある人はほぼいません。ほんのちょっとのやる気で知識の差はすぐに埋められますし、サポート体制と実際に手を動かせるプロジェクトも揃っているので、私のように文系出身のIT未経験者でも不安がらずに、「とにかくやってみよう」とアグレッシブに挑戦してほしいです。