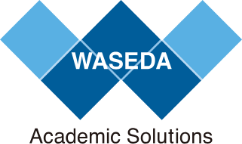早稲田大学のグループ企業として、
「情報」「教育」「国際」「研究」など
大学運営におけるほぼすべての領域で業務を行う
早稲田大学アカデミックソリューション
(以下、WAS)。
その中で「情報」を担う
IT推進部の各チームでは、
多様なバックグラウンドと専門性を持った
メンバーが活躍しています。
今回はコンテンツ企画チームで主に
受験生向けの入試広報サイトを担当する
T.H.さんにお話を伺いました。
学生や教員へ、
より質の高い授業動画などのコンテンツ、
そして視聴環境を届けるために日々奮闘する彼は
何を目指しているのか。
その背景にある想いを伝えます。

2023年入社
IT推進部 コンテンツ企画チーム
T.H.
*所属チームはインタビュー当日の配属先です

チューター時代の
情熱を忘れられず
教育業界へ

教育業界に関わりたいという強い想いから、WASへ転職をされたと伺いました。その理由を教えてください。
学生時代に予備校でアルバイトをしていたこともあり、元々、教育業界に興味がありました。しかし、働き方などの理由から一度は新卒でインフラ業界に入社。そこで1年ほど働いたのですが、やはり教育業界への想いを断ち切れませんでした。
学生時代はサテライト塾でチューターを行っていたので、講師のように学生へ直接教えていたわけではありません。学生へ学習指導をしたり、ときには校舎運営に関わったりしていて、そのことにやりがいを感じていたので、その経験が教育業界全体を支える仕事をしたいと思うきっかけになったように思います。
大学運営におけるほぼすべての領域で大学を支えるWASなら、学生時代の経験を活かすことができ、自分のやりたいことにも取り組めると思い、転職を決意しました。また、WASという名前だけど、早稲田大学だけではなく、そのスキルやノウハウを外販し、他の大学の業務支援を行っている点も後押しとなりました。
やっと希望の教育業界で働けることとなりましたが、入社後はどのような業務を担当されていますか。
入社後はIT推進部 コンテンツ企画チームで、各種授業動画コンテンツの制作や入試広報サイトの企画制作・運用などに携わっています。
私は主に、受験生向けに早稲田大学の情報を発信する入試広報サイトの運営を行っています。早稲田大学に興味を持ってもらうために、どんなコンテンツをどの位置に掲載すると見やすいのか、そのコンテンツはどのような内容、見せ方だと魅力に感じてもらえるのかといったことを、大学職員や制作会社の方と相談しながらサイトを運営しています。
掲載するコンテンツとは具体的にどのような内容のものがあるのでしょうか。
早稲田大学の学生生活やキャンパス、学部紹介など様々なコンテンツがあります。大学が制作してサイト掲載だけを担当することもありますし、私たちが主導で制作することもあります。
例えば、2024年には奨学金制度や英語カリキュラムの紹介動画を作りました。大学の要望を実現できる制作会社を選定し、それぞれの目的に合った学生にインタビューを実施。伝えたいことが最も伝わるように制作会社さんに編集してもらい、入試広報サイトに掲載しました。
大学と制作会社を
つなぐ架け橋として
専門性を発揮

大学と制作会社をつなぎ、大学側の要望を形にしていくコンテンツ企画チームは大学にとってどんな存在だと思いますか。
コンテンツ企画チームは、大学が動画やサイトなど何かコンテンツを作りたいと思ったら、最初に相談する窓口です。相談に来られた段階では、やりたいことがふわっと曖昧なこともありますが、そこから本当にやりたいことを実現できるように、依頼者自身も気づいていなかったニーズを拾い、情報を引き出していくことも私たちの役割だと考えています。
コンテンツ制作においては、大学の要望を制作会社に伝え形にするディレクターとしての役割を担っていますが、間に立つ立場として大事にしていることはありますか。
私たちコンテンツチームの役割は、大学と制作会社の間をつなぐ架け橋となることです。大学職員は学生の、制作会社は動画制作の、それぞれの領域におけるプロフェッショナルですが、見ている視点が異なります。
だから、大学と制作会社の間に立ち、どちらの立場も理解しながら広い視野で判断することを心がけています。大学側のニーズを汲み取り、制作会社に噛み砕いて伝えたり、早いタイミングで大学職員にイメージを提示して具体物を見ながら会話を進めたり、両者それぞれの特性を理解して、大きな認識齟齬が出ないように橋渡しします。
動画などのコンテンツを見る視聴者に対してはどうでしょうか。意識していることはありますか。
入試広報サイトに関して言えば、サイトを見るのは高校生をはじめとする受験生と、その親世代の方々が大部分を占めています。作り手の考えだけで動画を作っても見てもらえないので、予備校での経験を活かしながら、受験生、親世代に見てもらえる動画となるようにこだわっています。
例えば、10分の動画よりも、3分、5分といった短い動画の方が見てもらえるため尺を短くしたり、動画の最初で見る見ないを決める傾向があるため、冒頭に視聴者を惹きつける要素を入れたり、できる限り見てもらえない理由を取り払えるように制作会社に意見を伝えます。
ライトボードでの実現を目指す
新時代の動画授業

授業動画の制作に携わることも多いコンテンツ企画チームでは、動画授業の価値をより高めるために新たな取り組みを始めていると伺いました。その内容を教えてください。
今、私たちがご紹介している新しい講義ツールとして「ライトボード」というものがあります。ライトボードは海外の有名大学で急速に普及し始めていたもので、WASでも設計から開発・製作を行い、現在は早稲田大学内の収録スタジオにも導入しています。
ライトボードについて詳しく教えてください。
ライトボードの仕様としては、ホワイトボードの白板部分が透明の板になっています。その透明な部分に文字を書くことで正面から撮影することができるため、視聴者はまるで空中に文字を書いているような未来的な板書を見ることができます。
説明をする教員の表情や動きも見えるため、学生もその熱量を感じることができ、情報も伝わりやすい新時代の講義ツールとして可能性を感じています。
実際にライトボードを使った教員が学生に取ったアンケートでも、見た目のスタイリッシュさと説明のわかりやすさが印象に残っていたようで、他大学にも広く使っていただきたいと思い、最近は外販活動にも力を入れ始めています。
ご自身もライトボードの外販活動を行っているのですか。
はい。私もライトボードの外販打合せに同席したり、オンライン打合せの際はライトボードを活用しながら機能説明をしたりしています。
私はライトボードを使ってもらうことで、学生にとっても、教員にとっても、より質の高い授業を提供できると信じています。ですから、多くの大学にライトボードの存在を知ってもらい、導入してもらうことに、積極的に関わりたいと思っています。
業界全体に価値を提供できる
それが教育現場を裏から支える魅力

コンテンツの制作からライトボードの外販まで幅広い業務に関わっていますが、この業務の魅力はどんなところにあると思いますか。
学生時代は授業内容のわかりやすさ、面白さばかりを考えていましたが、この業務を経験して初めて、学生が授業で動画を目にするまでの裏側を知りました。
たとえば、授業で使う動画においても、配信されるまでには様々な工程があります。講義資料の準備をし、収録方法を検討し、撮影をする。視聴しやすい時間に動画を分けて、字幕を付ける。さらに学生の皆さんが視聴しやすくするために、映像に見出しを設定したり、注目してほしいポイントにはキーワードを出すなどの工夫も施します。そのあと、その完成した授業動画を受講システムに登録して配信されてはじめて、学生の皆さんが視聴ができるのです。
コンテンツ企画チームでは、コンテンツを制作することはもちろん、ライトボードのように作ったコンテンツを学生へ届けるためのツールや届け方にまでこだわることができます。「学生に何を伝えたいか」という抽象的な想いを具体的な形に変え、最も伝わる形で届けるという一連の活動すべてに関われる場所はそう多くはありません。
しかも、WASは外販活動にも積極的なため、早稲田大学というひとつの大学だけでなく、大学業界全体への働きかけも可能です。学生からは直接見えない業務かもしれませんが、コンテンツ提供という側面から、大学業界全体に貢献できる場所で仕事ができることは、私にとって魅力しかありません。
強い想いをもって教育業界に関わられていますが、最後に教育業界に興味を持つ方へのメッセージをお願いします。
こうした教育現場を裏側から支えることに興味のある方、コンテンツを届ける相手を想像しながら、「こう受け取ってほしいな」「ここに面白さを感じてもらえたらいいな」と想像を形にしていくことを楽しいと感じる方にこの仕事は向いています。
しかも、ここはコンテンツを作るだけではありません。見てくれる方に届けるところまで責任を持って関われる、その仕組み作りから挑戦できることを楽しいと思える方は、積極的に挑戦してほしいです。