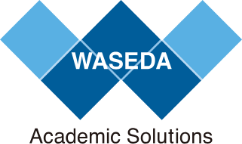早稲田大学に止まらず、
全国の大学の変革をITの力で支援する
フロントランナーになることを目指す
早稲田大学アカデミックソリューション
(以下、WAS)のIT推進部。
当部署では、多様なパートナーと共に
大学のITインフラ設備や
利用者支援も担っています。
今回お話を伺ったのは、
教職員・学生のIT環境を支援する
ITサポートチームのR.Y.さん。
大学時代からサークル活動で
受験生サポートを行うなど、
学生と直接関わることに興味のあった彼女は、
日々どのような判断軸やこだわりを持って
約500もの教室を管理し、
複数の協力会社をマネジメントしているのかー。
その実態を聞きました。

2023年入社
IT推進部 ITSチーム
R.Y.
*所属チームはインタビュー当日の配属先です

快適な学生生活を提供したい
その想いがすべての原動力

大学業界かエンタメ業界で働くことを希望されていたと伺っています。その理由を教えてください。
大学業界とエンタメ業界を選んだのは、自分の好きなことを仕事にしたいと考えていたからです。特に大学と関わる仕事に興味を持ったのは、学生時代に大学のオープンキャンパススタッフや受験生サポートを行うサークルで活動していたことがきっかけです。漠然とですが、快適な学生生活のサポートを仕事にできればと考えていました。
両業界で就職活動を進め、最終的にWASヘ入社することを決めたのはなぜでしょうか。
決め手はWASの最終選考でした。最終選考は「ホスピタリティ」に関する経営陣へのプレゼンで、私は大学時代のサークル活動について発表しました。
学生時代はコロナ禍だったため、対面で情報を得られない受験生に向けてホームページを作成したことを伝えたのですが、資料にその二次元コードをつけたところ、面接官は自らその二次元コードを読み取り、積極的に質問やアドバイスをくれたのです。
「学生目線で考えるともっとこうしたらいいよ」という、前向きな意見をたくさん投げかけてくれる真摯な姿勢に惹かれ、この人たちとなら一緒に学生生活をサポートできそうと思えたので、WASへの入社を決めました。
入社当初は学生時代の経験を活かせる部署を希望していたと伺いました。IT推進部への配属が決まった時は、率直にどのように感じましたか。
当初は学生と直接関わる窓口業務に興味を持っていたので、IT推進部と聞いた時は、正直、自分に務まるのか不安でした。学生時代は文学部で日本文学を専攻していたため、特筆するようなITスキルはありません。さらに、女性が多い部署が大半のなか、IT推進部は男性が多い部署です。環境的な不安も少なからずありました。
入社して1年経った今、その不安な思いは変わりましたか。
1年経った今では、その心配は杞憂に終わりました。IT推進部は性別や年次を気にすることなく働ける環境ですし、誰に対しても対等に接する人ばかりです。学生生活に直結する部分に関わることもたくさんあり、自分が学生の役に立っていると実感できる瞬間が多いので満足しています。
多様なパートナーとの密な連携で
快適な学び空間を支える

IT推進部配属後はITSチームで活躍されていますが、具体的にどのような業務を担当されていますか。
利用者向けのヘルプデスク、早稲田大学が提供する各種サービスで使用するユーザID、そして教室のプロジェクターやスクリーンといったAV環境の3つを主に管理する立場として、それぞれマネジメント業務を担っています。
それぞれの業務について詳しく教えてください。
1つ目のヘルプデスクでは、10名弱の専門スタッフがメールや電話による利用者からの問い合わせ全般に対応してくれています。問い合わせ内容として想像しやすいのは、学生からの科目登録に関するものでしょうか。私はその方々の管理や稼働調整を行っており、時には利用者からの問い合わせ対応に必要な情報について大学側との連携役なども担っています。
2つ目のユーザIDですが、早稲田大学に籍を置くすべての学生・教職員がユーザIDを持っています。利用者はIDを使って大学のポータルサイトからお知らせの確認、授業支援システムなどが利用できるため、大学生活に欠かせません。入退学に合わせて迅速に正しく発番・廃番できるよう、こちらも10名ほどの専門スタッフと連携し、進捗管理を行っています。
3つ目のAV環境管理では、教室の規模や利用頻度を参考にプロジェクターやスクリーンといったAV機器の更新や新規導入を進めています。学生にとっての見やすさと教員にとっての使いやすさを追求できるよう、大学が立てた教室の改修計画に沿って仕様書をまとめ、施工会社を選定し、改修工事の施工管理や大学職員のサポートなどを行っています。
早稲田大学には9か所のキャンパスと2か所の高等学院に、のべ800以上の教室があります。主に学生の授業がない、春休みや夏休みなどを使って教室の改修工事を行っており、今年の夏は早稲田キャンパスと所沢キャンパス、さらに早稲田大学高等学院を合わせて50教室ほどを改修しました。
円滑な業務遂行のため
客観的に判断することを常に意識

業務毎に求められるスキルや知識も異なると思いますが、この業務のやりがいはどこにあると思いますか。
私が担当している業務は、学生が快適な学校生活を送るために必要不可欠な基盤となるものばかりです。
教室に対してスクリーンが小さく授業が見えづらい、履修科目に関する疑問を解決できず登録を完了できないなど、学生生活に関する小さな問題はたくさんあります。しかし、パートナーと先回りしてそれらの問題を解消することで、学生に快適な学び環境を提供できることがこの仕事の一番のやりがいだと感じています。
また、この業務のパートナーは、大学職員や専門スタッフ、施工会社など多岐に渡ります。対応すべき事案が発生したときに、それぞれのパートナーとの調整がスムーズに進み、例えば教室改修の完成のようにゴールが目に見えることもやりがいを感じられる点です。
それぞれの業務で関わるスタッフは専門性も役割も異なる、その領域のプロフェッショナルばかりだと思います。パートナーと共に幅広い業務を推進するなかで感じる大変さはどんなことですか。
AV環境管理では、管理する教室数の多さゆえに教室毎の機器を把握することや、それぞれの教室に適した機器を見極めることが大変です。
また、AV機器の協力会社を始め、ヘルプデスクやユーザIDの管理に関わるスタッフは皆さん社歴が長く、年上の方ばかりです。知識量も豊富で、各ケースへの対応も私より慣れていることが多いプロフェッショナルのため、マネジメントすべき私が最も教えてもらうことの多い状況に、もどかしさを感じることもあります。
そんなプロフェッショナルなパートナーとのコミュニケーションにおいて、心がけていることがあれば教えてください。
経験値が足りない部分は知識で補うしかありません。定例会議でわからないことがあれば、なるべく直接顔を合わせて素直に質問するようにしています。
また、私たちは大学職員と窓口対応いただくスタッフや教室改修を担当する施工会社との間で調整をすることも求められます。どちらかに肩入れするのではなく、それぞれの主張をしっかり聞いて、最適解を導けるように客観的に判断することを心がけています。
50教室の改修を
やり遂げたことで
得られた成長を実感
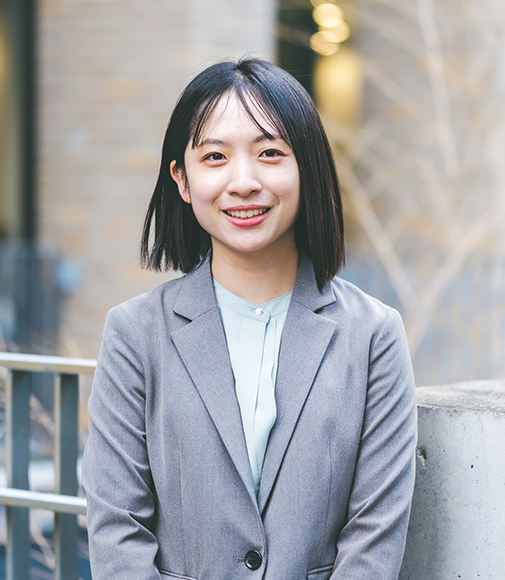
入社して1年、様々な業務に携わってこられたと思います。これまで携わった業務の中でもっとも記憶に残っている業務は何ですか。
今年の夏、50近い教室の改修を主担当としてやりきったことがもっとも印象深く、自分の成長を感じた瞬間としても記憶に残っています。
教室を改修する際は、それぞれの教室毎に設置するAV機器の構成を考え、施工会社を選定し、施工までのコミュニケーションを取り、実際に問題なく工事が完了するまでを見届けることに加え、それに付随する業務もたくさん発生します。
例えば、学部の担当者と工事日程を調整したり、工事期間中の車両申請を行ったりと、教室数が増えるにつれてパートナーもどんどん増えていきます。どれか1つでも抜けてしまえば、期間中に改修を終わらせることができず、休み明けの学校生活に影響を及ぼすことになりかねません。
関係する多くのパートナーと密なコミュニケーションを取りながら、タスクを抜け漏れなくこなし、無事に完了できたことに今はほっとしています。また、この改修を通して、「この教室だとこんなAV機器が必要」だとわかるようになってきた自分に成長を感じています。
教室改修にあたり、他の大学を訪問し参考にすることもあると伺いました。どのような点に着目して観察するのですか。
Googleアラートを活用しています。新しい設備を導入した大学の情報がメールで届くように設定しておき、気になる大学には訪問依頼のメールを送っています。そして、訪問時には教室の収容人数に対してどんなAV機器を導入しているのか、この教室だと学生はどんな使い方をするのかという視点で見ています。
他の大学を見たうえで感じる早稲田大学の教室について、今後どのように変えていきたいと感じていますか。
私も決してオーバースペックなAV機器を求めているわけではありません。しかし、誰が見てもすぐに使えるシンプルかつ教室サイズに必要十分なAV機器を導入することで、1教室あたりのコストを抑えて、施工会社の協力も仰ぎながら改修できる教室数を増やしていきたいと思っています。
入社2年目にも関わらず、各領域のプロフェッショナルなパートナーとの業務をマネジメントする立場として、学生の快適な学び空間作りに力を発揮されています。多様なパートナーと共に、大学に関わる仕事がしたいと考えている学生へメッセージをお願いします。
この仕事の一番の魅力は、自分よりもスキルや経験を持つプロフェッショナルな方々と一緒に、快適な学生生活を下支えできることです。
誰もが学生のことを真剣に考えているからこそ、ときにパートナー同士がぶつかってしまうこともありますが、その間に立って着地点を見つけられるのも私たちの仕事の面白さです。
また、大学職員とは異なり、自分の大学だけでなく、他大学と関わる機会も多く、各専門会社を含めさまざまな職種の方と関われることも魅力です。
多様なパートナーと力を合わせて、多くの大学に関わる仕事をしてみたいと思う方と、ぜひ一緒に働きたいです。